ダイエットは、体重や体脂肪を減らすだけでなく、日々の生活や気持ちとの戦いでもあります。
我慢のしすぎでストレスがたまったり、モチベーションが続かなくなったり…私も何度も挫折を経験してきました。
ですが今回、「レコーディングダイエット」で自分の行動を“見える化”することが、ストレス対策や習慣化に驚くほど効果的だったと実感しています。
この記事では、ダイエットを続けるための「ストレス対策」と「習慣化のコツ」について、私自身の経験をもとに紹介しています。
この記事でわかること
- ダイエット中のストレスとうまく付き合う方法
- 我慢しすぎず続ける「ガス抜き」の考え方
- 習慣化を成功させる小さな工夫と仕組み
- 気持ちを楽にする考え方やモチベーション維持のヒント
ストレスを味方につけながら、無理なく続けられるヒントを見つけていきましょう。
ストレスは敵だけど、完全にゼロにはできない
ダイエット中にストレスを完全に無くすのは難しいです。食事制限や運動、生活リズムの調整など、普段とは違う行動を日常に組み込むことで、知らず知らずのうちに心や体に負担がかかっています。
実際に、過度な食事制限はストレスホルモン(コルチゾール)の増加を招くことが示されています。1)
また、慢性的なストレスが過食やリバウンドの引き金になることも報告されています。2)
だからこそ、「ストレスをゼロにする」よりも、ストレスとうまく付き合うという発想が大切です。多少の揺らぎがあっても良しとする心の余裕が、長く続けるための土台になります。
適度な「ガス抜き」が長続きのカギ
ダイエットを続けていくうえで、ストレスをためすぎないことが非常に重要です。
私も過去に週2回のチートデイ(好きなものを食べる日)を設けていましたが、気が緩みすぎて体重が増加し、継続が難しくなった苦い経験があります。
そこで現在は、週に1回までと頻度を制限し、家族と出かけた休日の昼食だけはある程度食べたいものを楽しむというスタイルに変更しています。その後の食事や運動でバランスを取ることを意識することで、体重管理もうまくいき、気持ち的にもストレスが軽減されました。
最近の研究では、計画的な「チートデイ」はモチベーションや満足感の維持に有効であることが示されています。 3)
また一部では、レプチン(満腹ホルモン)の分泌が増えることで代謝が促進されるという説もありますが、これはまだ確立されたエビデンスとはいえず、個人差を見ながらの運用が大切です。
つまり、チートデイは甘えではなく「継続のための戦略」として取り入れることができるのです。ただし、「頻度」と「内容」はしっかりコントロールすることが前提です。
睡眠の質もストレス対策に効果的であり、睡眠が浅いと食欲ホルモンの乱れやストレスの増加に直結します。
👉 ダイエットと睡眠の深い関係とは?
続けるためには「仕組み」と「ごほうび」
モチベーションだけでダイエットを続けるのは、想像以上に難しいものです。
日々の忙しさや気持ちの波に流されると、意欲はすぐに低下してしまいます。
そこで大切なのが、「続けられる仕組み」と「小さなごほうび」の工夫です。
新しい習慣が定着するまでには平均66日(約2か月強)かかるという研究結果⁴もあります。
つまり、仕組みを整え“自動化する”ことが継続のカギだといえます。
私が実践している継続の工夫
- 朝食を毎日固定メニューにする → 栄養バランスが安定し、迷うこともなく習慣として根づきます
- 毎日の体重・食事を記録して“見える化” → 微妙な変化を確認でき、行動の振り返りに役立ちます。👉 レコーディングダイエットの始め方とコツ
- アンダーデスクバイクによる“ながら運動” → 負担感が少なく、作業しながら続けられます👉 運動なしでも痩せられる?私が選んだ“ながら運動”の方法
- 週に1回、家族との外食を自分へのごほうびに → 楽しみを持つことで継続力が高まります
このように、モチベーションに頼るのではなく、日常に組み込んで「頑張らなくても続く仕組み」を整えることが大切です。
完璧を目指すのではなく、7割の達成でもOKと思える“余白”を持つことも継続の秘訣です。
👉 ダイエットの目標設定の考え方
ビリーのひとりごと
- ストレスは完全になくすのではなく、うまく付き合う工夫が大切
- 適度なガス抜きは、継続のための「戦略」として取り入れる
- モチベーションだけに頼らず、仕組み化やごほうびで習慣化をサポート
- 完璧を求めず、7割できたらOKという「ゆるさ」が長続きのコツ
ストレスと上手に付き合うためには、「食事の考え方」や「記録の習慣」など、ダイエットの基本を押さえておくことも大切です。
👉 続けるための“基本の習慣”については、こちらの記事で詳しく解説しています
▶︎ 医師が実践して気づいたダイエットの基本|続けるための3つの習慣 - 「どうせ無理」ではなく「ちょっと試してみよう」の一歩が変化のきっかけに
1)Tomiyama AJ et al. Psychosomatic Medicine, 2010; 72(4): 357–364.
2)Schaumberg K et al. Eating Behaviors, 2016; 22: 5–9.
3)Rita Coelho do Vale et al. Journal of Consumer Psychology 26(1); January 2016: 17-28.
4)Phillippa Lally et al.European Journal of Social Psychology. 2010;40:998–1009.
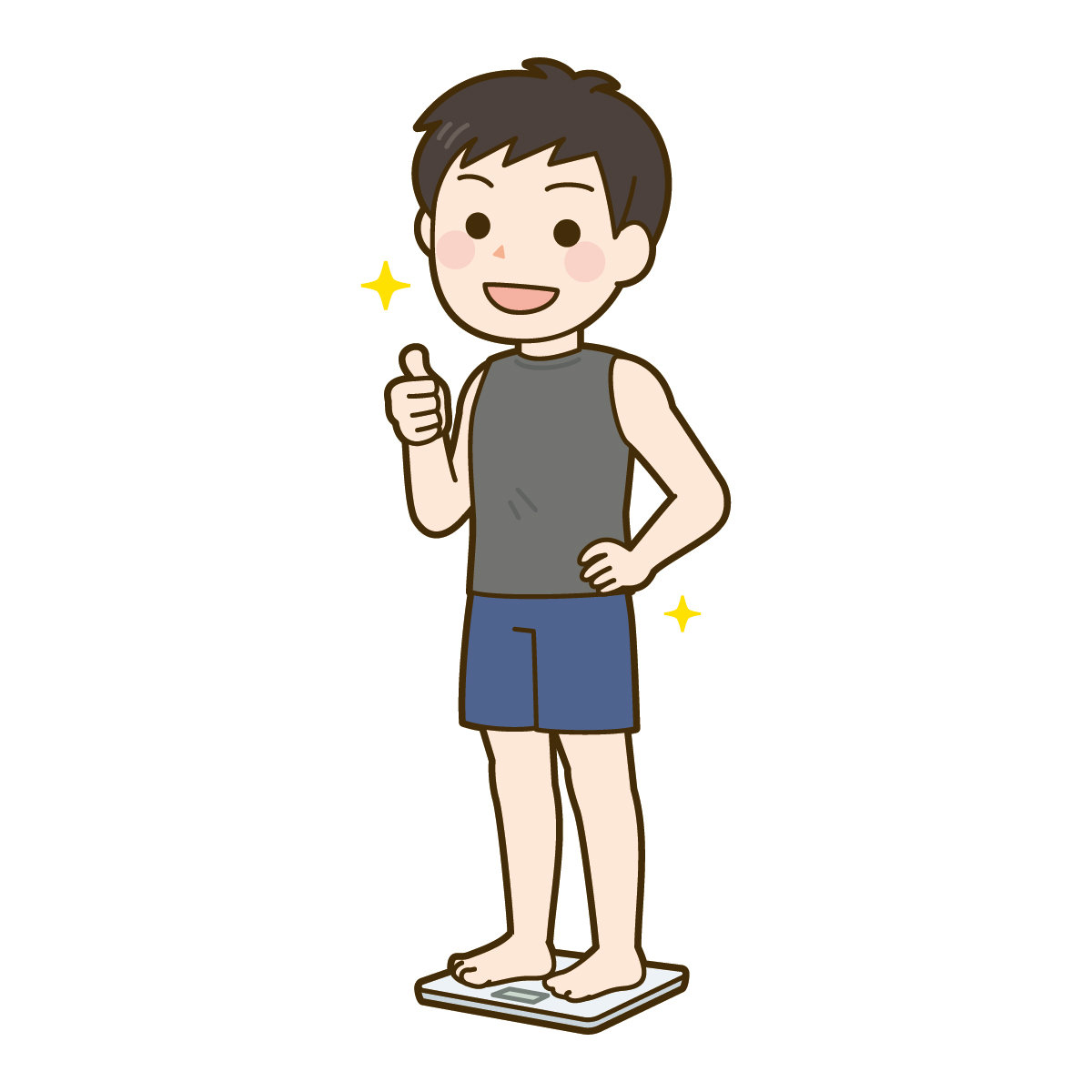
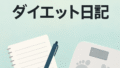
コメント